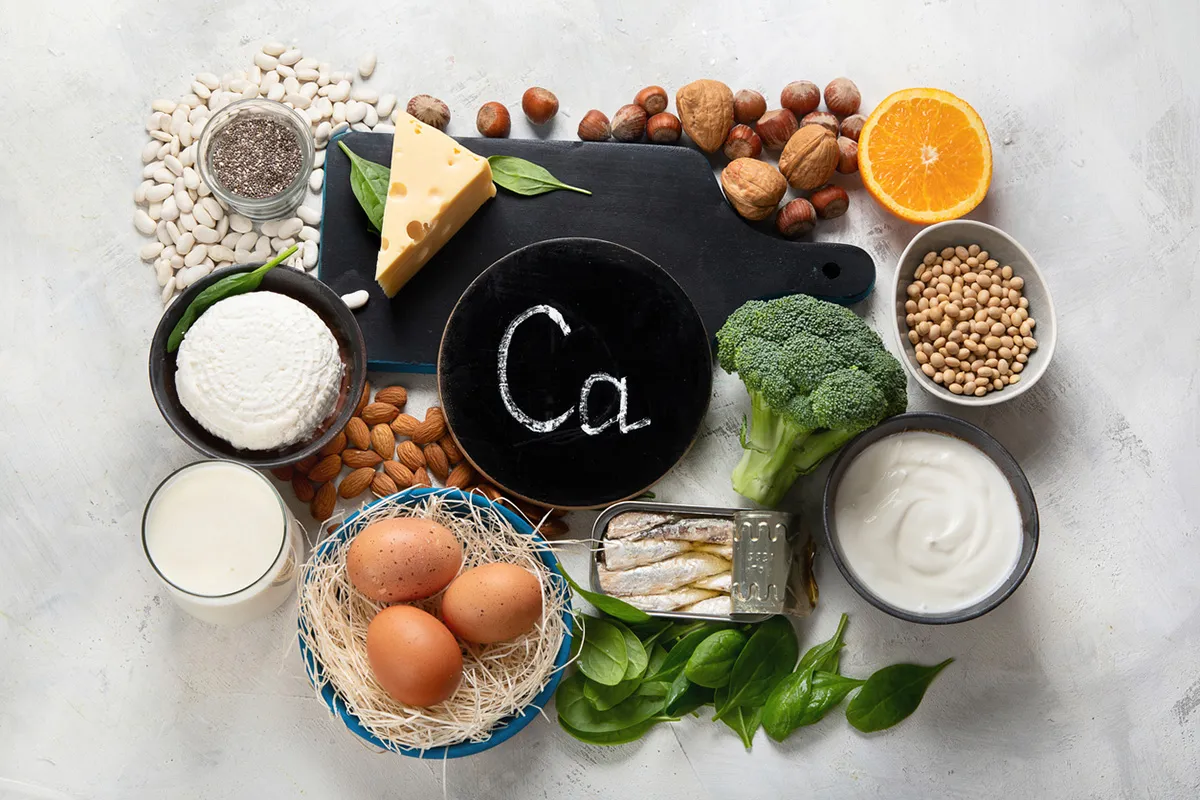日本のお菓子市場にグミが登場した当初、弾力のある独特の食感は多くの人に衝撃を与えました。しかし、今やグミは身近なお菓子として私たちの暮らしに定着し、ガム市場を追い越すほど人気が高まっています。
グミはなぜこれほど広く受け入れられたのでしょうか。また、グミ特有の食感はどのように生み出されるのでしょうか。グミの歴史や作られ方を紹介しつつ、日本のグミブームの背景を探ります。
☆グミと同じく人気のチョコレート。バレンタインデーに贈るようになったワケとは?詳しくはこちらをご覧ください。
・バレンタインデーは何の日?由来は?海外ではどんな習慣がある?
「噛む」ために誕生した?グミの歴史は100年前のドイツから

グミは今から約100年前、1920年代にドイツで誕生したお菓子です。日本でグミの大ブームが起こったのはここ数年のことですので、これほど長い歴史があるお菓子だと聞くと意外に感じられる方も多いのではないでしょうか。
当時のドイツでは虫歯や歯周病など歯の病気が流行しており、子どもたちがやわらかいものを好んで食べ、咀嚼力が低下していることが主な要因だと考えられていました。実際、噛むときに分泌される唾液には口の中をきれいにしたり、血行を促すといったはたらきがあり、歯の病気の予防だけでなく全身の健康維持にもつながるとされています。※1
そこに注目したドイツのHans Riegel(ハンス・リーゲル)氏が、子どものうちからしっかり噛む習慣をつけられるようにと開発したのがグミでした。彼が出身地のボンに創業した会社は、今や世界最大のグミメーカーとなっています。
なお、「グミ」という名前はドイツ語で「ゴム」を意味する「gummi」に由来しています。確かにグミはほかのお菓子にはない強い弾力を持ち、まるでゴムのように噛み応えのあるお菓子といえます。特に、当時のグミは「噛む」という目的が重視されていたため、今私たちが食べているグミよりもはるかに硬かったようです。※2
食感や栄養にも注目
ガムを超えたグミの人気の秘密は種類の多さ

日本でグミが登場したのは1980年代で、特に新型コロナウイルス感染症の流行中に売上を大きく伸ばしました。2013年と2023年を比較すると、この10年で2.6倍に増加しています。グミ市場は今やガムを追い抜き、1000億円を突破する規模にまで拡大しているのです。※3
なぜグミはこれほど多くの支持を得られたのでしょうか。ひとつの要因は、グミが「衛生的」なお菓子だと受け止められたことにあるようです。グミはガムと同じ噛むお菓子ですが、食べた後にゴミが出ないため、衛生面に注目が集まっていたコロナ禍にも安心して食べられるお菓子として選ばれたのでしょう。
また種類が豊富なのもグミの魅力で、ハード系からソフト系まで、さらに砂糖や酸味のあるパウダーなどでコーティングされたものもあります。定番の果汁味をはじめ、最近では和風グミも登場するなど味のバラエティも富んでいます。また、栄養面や機能性を訴求したグミもあり、ビタミンなどの補給のため、グミをつまむという人もいるかもしれません。
リング状、ロープ状、裂けるグミと形状もさまざまで、SNSではグミで「アート作品」を作る人も見かけます。お菓子メーカー各社から趣向を凝らしたグミが数多く発売されており、誰でもお気に入りのグミを見つけやすいこともブームを後押ししているといえそうです。
☆咀嚼に関するこちらの記事もご覧ください。
・子どもの咀嚼力は脳の発達や歯並びにも影響する?噛む力の大切さとは
・「咀嚼」はカラダにいい?お煎餅の咀嚼音「パリパリ」は世界共通か?
ハードグミ、ソフトグミ…独特の弾力はどこから?
意外と知らないグミの原材料

ところで、グミ特有の弾力のある食感はどのように生み出されるのでしょうか。その疑問を解くカギは、グミの原材料のひとつ「ゼラチン」にあります。コラーゲンから作られるゼラチンが、独特の噛み応えのもととなっているのです。
ゼラチンは、ゼリーを固めるためのゲル化剤として広く知られています。ゼリーはスプーンですくうとやわらかく崩れ、口の中でとろける食感で、同じゼラチンを使ったお菓子でありながらグミとはまったく異なります。この違いはグミとゼリーの水分量の差によるもので、一般的なゼリーの水分量はゼラチン5gに対して250〜300mlですが、グミの水分量はその3分の1以下です。この水分量の少なさがグミの弾力を生み出しているのです。※4
このように、ゼラチンの量と水分量の割合の違いによって食感が変わるため、同じグミでも含まれる水分の量が多いとやわらかいグミに、少なければ硬いグミになります。人によってハード系とソフト系に好みが分かれますが、日本では最近、噛み応えのあるハード系グミの人気が高まっているようです。硬いグミを噛むと集中力が増す、眠気が覚める、イライラがしずまるなどと感じる人も多いといいます。※5
一方で、米粉を使ってこれまでにないもっちりとした食感を表現したグミも登場しています。今後も、さまざまな材料の特性を活かした新たな食感のグミが開発されるかもしれません。
☆おもちのようなグミ「もちきゅあ」には女性に不足しがちな栄養成分も。詳しくはこちら。
手作りグミレシピやアレンジレシピも
グミをもっと楽しむ方法

グミは、身近にあるものを使ってご家庭で作ることもできます。果汁ジュースやかき氷のシロップと、粉ゼラチン、砂糖を混ぜて加熱し、型に流し入れて冷やせば出来上がり。ゼラチンと水の分量次第でお好みの硬さに作れます。
完成したグミはもちろんそのまま食べても良いのですが、たまにはアレンジして楽しんでみてはいかがでしょうか。カラフルなグミを炭酸水に浮かべたり、ゼリーやヨーグルトに混ぜたりするとテーブルが華やかになり、おやつタイムが楽しくなります。果物のように、生ハムと合わせていただくという食べ方もあるようです。
ただグミには糖分が多いので過剰摂取には注意が必要です。また弾力の強いグミを子どもに食べさせる場合は十分注意しましょう。そのうえで、これからもまだまだ続きそうなグミブームをぜひご家族で楽しんでくださいね。
☆こちらもあわせてご覧ください。
・ドルチェって何?スイーツやデザートとの違い。本場の味を再現したお菓子も!
【参考文献】
※1 神奈川県歯科医師会
https://www.dent-kng.or.jp/colum/basic/96/
※2 ドイツ大使館
https://www.young-germany.jp/2021/05/susschnabel/
※3 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO87243610Q5A310C2TB1000/
※4 農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2403/spe1_02.html
※5 山陰放送
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/bss/1773094?page=3
-

-
ライタープロフィール
澤 晶子(サワ アキコ)
WEB編集者・ライター
長年、学習塾・家庭教師勤務。フレンチ・イタリアンレストランでの勤務経験も豊富。趣味は食べ歩きと料理。季節のグルメのお取り寄せにも目がなく、特に地方限定銘菓が大好きです。
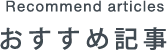

- 1
- 2
- 3
- 4