生涯にわたり健康な歯を維持することを目指す「8020運動」をご存じでしょうか?
いつまでも自分の歯で噛み、食事を楽しむためには、口腔ケアを心がけて歯の健康を守ることが大切です。口腔ケアには歯磨きだけでなく、咀嚼も大きく関わっています。
今回は、8020運動の概要や口腔ケアと咀嚼の関係を解説し、咀嚼回数を増やして歯の健康維持につなげる方法をご紹介します。
歯を守ることで生活の質を向上させる「8020運動」とは
8020(ハチマルニイマル)運動とは「80歳になっても自分の歯を20本以上保つ」ことを目指し、厚生労働省と日本歯科医師会の主導によりスタートした取り組みです。
「80歳」という年齢は、8020運動が提唱された平成元年当時の平均寿命に基づいています。現在は平均寿命が大きく延びているため、「80歳」は具体的な数値目標というよりは「高齢期」を象徴する意味に変化しており、8020運動は「高齢期を健康に過ごすこと」を目指す取り組みと捉えられるようになってきています。
またこれまでの調査・研究により、親知らずを除く28本の歯のうち20本以上が残っていれば、硬い食品もほぼ問題なく噛めることがわかっています。つまり、「20本」というのはしっかり噛んで健康的な食生活を送るための目安といえるでしょう。※1
平成29年の「国民健康・栄養調査」では、歯と口腔の健康に関する調査も行われました。20本以上の歯が残っている人の割合は、49歳までは95%を超えていますが、50代以降は徐々に低下していきます。
また、「何でも噛んで食べられる」と回答した人の割合も、49歳までは90%以上を示していますが、50代以降は年齢とともに低くなっています。※2この結果からも、歯の本数が噛む力の維持に影響していることがわかります。
食べることは健康に直結しており、また生活の質向上にもつながっています。いつまでも自分の歯で食事を楽しむためには、適切な「口腔ケア」で口の機能の維持・向上を目指すことが重要です。
歯の健康維持には噛むことが大切!口腔ケアと咀嚼の関係性

口腔ケアといえば、歯ブラシや歯間ブラシ、デンタルフロスなどを使用した「口の中の掃除」が一般的に知られていますが、実は唾液も口の健康維持に重要な役割を果たしています。
口の健康に関する悩みのなかでも、特に虫歯を気にしている方は多いのではないでしょうか。虫歯ができるのは、虫歯菌が食べ物に含まれる糖質を栄養源に増殖し、酸を作り出して歯を溶かすためです。唾液には、虫歯菌を洗い流したり、虫歯菌の影響で酸性に傾いた口腔内を中和したりして虫歯になりにくくする働きがあります。※3
私たちは食事のとき、口に入れた食べ物を歯で噛み切り、細かく砕いたりすりつぶしたりして飲み込みやすい形にしています。この一連の動作が「咀嚼」で、咀嚼によって口の中の粘膜が刺激されると唾液の分泌が促されます。よく噛んで食べることで唾液の量が増えれば、口腔ケアにも役立つでしょう。
ちなみに「虫歯」「むし歯」は、医療用語では「う蝕」または「カリエス」といいます。「虫」が「歯」を痛めるのではなく、「蝕む」の音から派生して広くは「むし歯」が使われています。
徳川家康も大事にしていた「よく噛むこと」。
咀嚼回数を増やす方法を紹介

咀嚼の大切さを教えてくれる偉人として忘れてはならないのが、徳川家康です。江戸時代の平均寿命は40歳前後だったと考えられていますが、徳川家康は75歳まで生きたといいます。さらに、74歳のときには大坂夏の陣に出陣しており、ただ長生きしただけでなく「健康長寿」であったことがうかがえます。
徳川家康は人一倍健康に気をつかっていたようで、天下を取ったあとも麦飯と味噌を中心とした粗食を続け、医薬の知識にも長けていたとされています。食事のときには「よく噛むこと」を大切にし、一口で48回噛んでいたともいわれます。これが、徳川家康が健康で長生きできた要因のひとつだったのかもしれません。※4
咀嚼回数は時代とともに明らかに減少しており、戦前は1回の食事で1420回だったのに対し、現代は620回と半分以下に減少しているとの報告もあります。※5
咀嚼回数を増やすためには、調理方法や食べ方を工夫しましょう。噛みごたえが残るよう食材を大きめにカットするほか、煮物よりも焼き物や生食を選ぶと食感が残り、咀嚼回数を増やせます。また薄味にすれば、食材本来の味を感じようとして自然に噛む回数が増えるでしょう。
食べるときには口いっぱいに食べ物を詰め込まず、一口の量を少なくすると咀嚼しやすくなります。時間をかけてよく噛むために、一口ごとに箸を置くのもよいでしょう。テレビを見たりスマートフォンを操作したりしながら食べる「ながら食べ」を避け、食事に集中することも大切です。
噛む力を鍛え、健康な歯を維持する食べ物の選び方

食材選びを工夫することでも咀嚼回数を増やせます。噛む力が必要な歯ごたえのある食材、たとえば繊維質が多い根菜や海藻、きのこ、弾力のあるこんにゃくや貝類、タコやイカ、水分が少ない切り干し大根やひじきなどの乾物を食事に取り入れてみましょう。
お米に雑穀を混ぜて炊くのもよい方法で、雑穀のもちもち、プチプチとした食感を楽しみながら食べると、無理なく咀嚼回数を増やせます。噛むことでおいしく口腔ケアできるよう、おやつにせんべいや煎り大豆、ナッツ類、するめ、ドライフルーツなどの歯ごたえのある食品を選ぶのもおすすめです。※6
歯磨きはもちろん、食事や間食の内容を工夫して咀嚼回数を増やすことも口腔の健康維持に役立ちます。いつまでも自分の歯で噛んで食事を楽しめるよう、日々の口腔ケアを心がけましょう。
☆間食で咀嚼回数を増やすには噛みごたえのあるおせんべいがおすすめです。こちらの記事もご覧ください。
・おせんべいとお茶は好きですか?復活するインバウンド!急増する外国人観光客のホンネ
・せんべいとおかき、あられの違い。うるち米って知っていますか?
・草加せんべいと南部せんべい なにが違う?お米と小麦で変わるおせんべいのルーツとは
☆咀嚼についてはこちらでも解説しています。ぜひご覧ください。
・咀嚼で増える?マイオカインという幸せホルモンに似た物質の正体とは
・「咀嚼」はカラダにいい?お煎餅の咀嚼音「パリパリ」は世界共通か?
【参考文献】
※1 厚生労働省 e-ヘルスネット
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/teeth/h-01-003.html
※2 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000351576.pdf
※3 日本歯科医師会
https://www.jda.or.jp/park/trouble/index02.html
※4 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXNASFK24034_U2A920C1000000/?msockid=1351120c16cc614a11d10728172660fc
※5 農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/minna_navi/topics/topics4_02.html
※6 独立行政法人 農畜産業振興機構
https://vegetable.alic.go.jp/yasaijoho/wadai/2107_wadai1.html
-

-
ライタープロフィール
いしもとめぐみ
管理栄養士。一般企業勤務を経て、栄養士資格を取得。病院給食、食品メーカーの品質管理、保育園栄養士を経験。現在は、栄養・健康分野の記事執筆を中心に活動中。日本ワインとおいしいものが大好き。
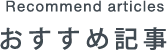

- 1
- 2
- 3
- 4







