勉強や仕事に打ち込んでいると、ひといき入れたくなることがありますよね。3時ごろのお茶の時間、あるいはおやつの時間、英語ではティータイムですが、いつ頃始まった習慣なのでしょうか。また世界のティータイムでは、どんなものが楽しまれているのでしょうか。日本と世界のティータイム事情、さらにティータイムのもたらす心身への効果についてご紹介します。
おやつの呼び名の由来は時間の「八刻(やつどき)」。
江戸時代のティータイムとは

「ティータイム」と聞くと何時ごろを思い浮かべますか?日本語では「お茶の時間」、あるいは「おやつの時間」でしょうか。午後3時ごろになるとお茶を入れてひと休みする、というイメージを持つ方も多くいらっしゃるかもしれません。
日本でのこの習慣の始まりは、江戸時代までさかのぼります。当時は1日2食だったため、朝食から夕食まではかなり時間があきました。しかもこの時代は、朝日が昇るとともに起きだして活動を始める人が多かったので、朝食はかなり早い時間帯だったはずです。畑仕事など体力を使う仕事をしていると、午後にはずいぶんお腹が空いたことでしょう。
そこで午後2時〜4時の間に小休憩をとり、軽食を摂って仕事に戻るという習慣が自然と生まれます。その時間帯は「八刻(やつどき)」と呼ばれていたことから、「おやつ」という言葉が生まれました。※1
江戸時代のティータイム、人々は何を食べ、飲んでいたのでしょうか。抹茶や煎茶はまだまだ高価で庶民には普及していなかったので、お茶は、お茶の葉を煮出したものや麦茶だったようです。砂糖を使用したお菓子も高価だったので、おやつは団子や煎り豆などが中心でした。江戸時代の人々もおやつの時間を楽しみに働いていたのかもしれませんね。※2
アフタヌーンティーを始めたのは
お腹のすいたイギリスの公爵夫人!?

お茶の本場・イギリスでは、モーニングティーに始まりナイトティーまで1日何回も紅茶を楽しみますが、有名なのはやはり15時頃に提供されるアフタヌーンティーではないでしょうか。
アフタヌーンティーでおなじみの3段重ねのスタンドは、18世紀に登場します。当時のイギリス貴族も食事は1日2回。しかもディナータイムは夜の8時ごろと遅めの時間帯だったので、やはり午後になるとお腹がすきます。
そこで空腹を我慢できなくなった公爵夫人アンナ・マリアという女性が、午後3時頃、自分の部屋にこっそりお茶と軽食を運んでもらうようになりました。そのうちに彼女は親しい友人たちをそのティータイムに招くようになり、次第にアフタヌーンティー、午後の社交の場として定着するようになったそうです。あの豪華な3段スタンドも、秘密のティータイム用の小テーブルに、たくさんのお皿を並べるための工夫から生まれたのだとか。※3
その頃、飲まれていたのは中国から輸入された半発酵茶(black tea)が中心でした。インドでアッサム種が発見されたのは19世紀になってから。ちなみに現代のイギリス家庭のティータイムでは、3段スタンドではなく紅茶とスコーンのセット「クリームティー」が定番です。※4
☆歴史の中で増えたお茶の種類はこちらをご覧ください。
・お茶の種類は100以上!発酵の有無で決まるお茶の分類とは
チャイにフィーカ お茶の種類も時間もさまざま。
世界のティータイム事情
午後のティータイムを大切にしているのは、もちろん日本やイギリスだけではありません。いくつかの国のティータイム事情をご紹介しましょう。
まずはヨーロッパ。フランスのティータイムは、子どもたちの学校が終わる4時ごろです。子どもたちは、お菓子や果物などのおやつ持参で迎えに来た保護者と一緒に、公園に寄ったり食べ歩きをしたりしながら「カトゥルール」を楽しみます。ドイツでは、おやつの時間は「カフェ―ツァイト」「クーヘン」と呼ばれます。ドイツはコーヒー文化の色濃い国ですが、ハーブティーやフルーツフレーバーティーも大人気。リフレッシュして午後の活動を再開できそうですね。
スウェーデンでは、午後3時ごろに甘いお菓子と紅茶やコーヒーを頂く「フィーカ」が大切なコミュニケーションの時間となっています。一方、スペインや南米は夕食の時間が夜の8時〜9時ごろとかなり遅いため、夕方5時ごろに「メリエンダ」を楽しみます。※5
アジア諸国に目を向けると、インドやスリランカなど南アジアはミルクで煮出して砂糖や香辛料を入れたチャイが好まれます。ベトナムではロータス・ティー(蓮茶)やジャスミン・ティー、またマレーシアではコンデンスミルクを使ったテー・タレッが定番です。
国ごとのライフスタイルや文化、気候によって様式は異なりますが、いずれの国でもティータイムは大切なコミュニケーションやリフレッシュの時間となっているようですね。
☆世界のお茶請けについてはこちらでもご紹介しています。
・スコーン、月餅、マカロン!万博開催の年に知りたい世界の「お茶請け」事情
疲れを感じたらおやつの時間で気分を一新!
ティータイムのメリット

午後にティータイムをもうけて、おやつを食べるのは、実は医学的な面からもメリットがあります。午後3時ごろといえば、仕事や勉強の集中力が途切れ、ちょうど疲れを感じるころ。そこで、すぐエネルギーに変わる糖分を取ることで、疲労回復やモチベーションアップに役立つのです。
また午後3時ごろは、脂肪をため込むタンパク質「BMAL1(ビーマルワン)」の活動がもっとも低下する時間帯です。つまり午後3時ごろは、甘いものを食べても太りにくい、おやつを食べるには適した時間帯だという説があるのです。罪悪感なしに甘いものを頂けるとなると、お茶の時間がもっと楽しくなりそうです。※6
もちろんティータイムのお供は甘いものでなくても構いません。ご自身が好きなおやつを適度に楽しむことが大事なのです。お茶とおやつを用意したらティータイムでリフレッシュして、午後の活動を充実したものにしていきましょう。
☆朝のティータイムについてはこちらをご覧ください。
・朝活は「朝茶」でリラックス 副交感神経がもたらす健康生活
【参考文献】
※1 一般財団法人日本educe食育総合研究所
https://www.educe-shokuiku.jp/news/shokuiku/oyatsu-20180419/
※2 米穀安定供給確保支援機構
https://www.komenet.jp/bunkatorekishi/bunkatorekishi08/bunkatorekishi08_1
※3 奈良県立図書館
https://www.library.pref.nara.jp/reference/kininaru/3044
※4 日本紅茶協会
https://www.tea-a.gr.jp/knowledge/tea_history/
※5 スペイン留学代行センター
https://www.spain-ryugaku.jp/soccer/column/2019/01/11/post-1068/
※6 独立行政法人 労働者健康安全機構北海道中央労災病院 治療就労両立支援センター
https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/kinrosyashien/pdf/H26-1.pdf
-

-
ライタープロフィール
澤 晶子(サワ アキコ)
WEB編集者・ライター
長年、学習塾・家庭教師勤務。フレンチ・イタリアンレストランでの勤務経験も豊富。趣味は食べ歩きと料理。季節のグルメのお取り寄せにも目がなく、特に地方限定銘菓が大好きです。
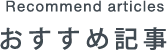

- 1
- 2
- 3
- 4







